こども教育研究家のこうへい先生です!
東京都世田谷区の教育現場で日々子どもたちと関わっています。
このブログは、子どもに関する悩み、運動に関する悩みを中心に記事を書いています。
↓↓
今日は「自己肯定感」についての記事です。
・自己肯定感が低くてチャレンジできない
・必要以上に自分を責める
・周りからのことばかり気になって自信が持てない
そんな子どもに、どんな関わりをしていくべきかを解説していきます。

⚪︎監修こうへい先生
体操競技歴17年、インターハイ•国体出場、海外大会優勝の経験あり。
運動指導のプロフェッショナル。おおしろキッズ体操教室教室長。
自己肯定感って何?
いろいろな表現の方法がありますが、自己肯定感とは《「I’m OK!」と思える感覚》のことです。
自己肯定感が高く、「私は私で進んでいける!」と思える方が人生うまくいくことが多いのは明白です。
「日本人は自己肯定感が低い」と言われたりすることも多く、近頃子ども教育のキーワードの一つにいなっている言葉でもあります。
自己肯定感を構成する6要素
自己肯定感はよく木で例えられます。
「自己肯定感」という言葉は少し抽象的でフワッとしているので、6要素に分解して説明していきます。
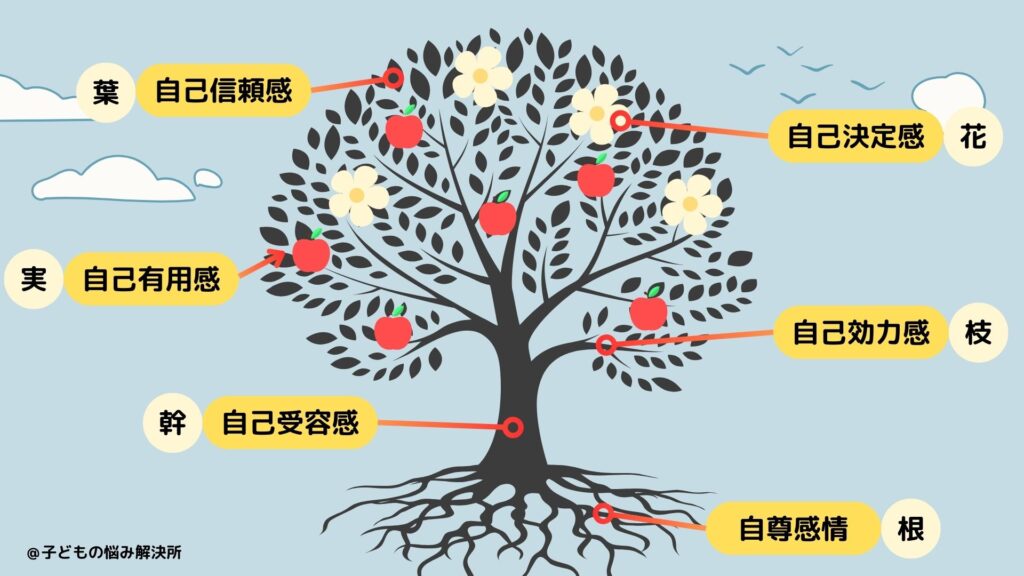
【根】自尊感情
自分には価値があると思える感覚
【幹】自己受容感
ありのままの自分を認める感覚
【枝】自己効力感
自分にはできると思える感覚
【葉】自己信頼感
自分を信じられる感覚
【花】自己決定感
自分で決定できる感覚
【実】自己有用感
自分は何かの役に立っているという感覚
自己肯定感は以上の6つから成ります。
まずは根っこの「自尊感情(自分は価値があると思える感覚)」を育む関わりをしていきましょう。
ここからは関わり方を紹介していきます。
子どもとの関わり方

①口を使わず耳を使う
多くの場合、子どもは助言を求めていません。
助言よりも、話を聞いてほしいんです。
まず耳を使って子どもの話を聞くようにしましょう。
子どもが何を感じているのか、どう思っているのか、耳を傾けましょう。
大人のその姿勢を子どもは見ています。
「自分の話を聞いてくれる存在」がいると、人は肯定されます。
②他人と比較しない
その子はその子、他人との比較をやめましょう。
「他人より優れている」という他者比較の物差しで自分の価値を測っていると、自分より優れた人が出てきた時に自分を肯定できなくなります。
「比べるのはいつも自分」です。
その子自身の物差しを作ってあげましょう。
③“普通という言葉を使わない
“普通”という言葉を使うのをやめましょう。
世の中に普通なんてありません。
子どもに使う“普通”という言葉が、彼らの中に「こうでないといけない」という像を作ってしまいます。
そうすると、“普通”と違う自分と出会ったときに、自己を認められなくなります。
“普通”という言葉はそういった危険を孕んでいます。
④罪を憎んで人を憎まず
子どもを叱るときは、「罪を憎んで人を憎まず」を決して忘れないでください。
叱られたとき、子どもによっては自分の人格を否定されたと感じる子がいます。
そうすると、自分で自分を否定するようになります。
「あなたは素晴らしいんだけど、あなたのやったことはいけなかったよ」と、人格と行動を切り離して子どもに伝えてあげてください。
⑤大好きを伝える
「大好き」という言葉は無条件肯定で最強の言葉です。
皆さんは1日に何回大好きを伝えていますか?
恥ずかしがらず、毎日伝えましょう。
無条件の大好きほど、その子を肯定してくれる言葉はありません。
⑥自己決定の機会を与える
些細なことでも、自己決定の機会を作ってあげましょう。
毎日は決定の連続です。
沢山の自己決定を通して「自分の人生、自分でコントロールできる!」という感覚を育んであげましょう。
自分の人生を決定できる自分に、価値を感じられるようになります。
まとめ
本日の記事、いかがでしたでしょうか?
大人の関わり方で子どもの様子は驚くほど変わります。
ぜひ紹介した関わりをしてみてください(^^)
今日はこんなところで!
それでは👋




コメント